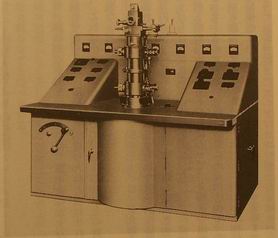風戸裕の短すぎた生涯[27]第8章 「電顕輸出に成功 世界シェア30%」①

1955年4月にツールーズで開催されたCNRS(フランス国立研究機構)主催の国際シンポジウム「電子光学における最近の技術的進歩」は日本の電子顕微鏡の世界的評価を不動のものとし、日本電子の世界進出を決定づけたシンポジウムだった。
【登場人物】
風戸 裕=フジで事故死したレーサー。
風戸健二=その父。日本電子創業社長。
帰国していた高橋昇のもとに、研究仲間のツールーズ大学フェルト教授から連絡が届いたのはシンポジウムの5ヵ月前だった。「日本からも代表的研究者を推薦してほしい」。
ツールーズにはCNRS総裁で、フランス唯一の電子光学研究所所長を兼ねるデュピュイがいて、電子顕微鏡の技術的研究を国家予算で強力に推進していた。このシンポジウムには、電子顕微鏡の生みの親、ドイツのボリス博士とルスカ博士(’86年ノーベル賞受賞)、超ミクロトーム(顕微鏡の試料切片切断装置)の創始者、スウェーデンのショストランド博士、その他、全世界の電子顕微鏡関係学会の重鎮が招待されていた。
彼らのシンポジウムといえば、真の討論がつきもので、厳しい質問に対して論理的に応酬できなければならない。日本から出席する者は名目だけの一流でなく、言葉ができなければ、かえって逆効果を生むことも考えられた。高橋にそこまで説明された風戸は、高橋自身と、伊藤一夫が参加することを提案した。これ以上の人選は考えられなかった。しかし、日本の代表である以上、日本顕微鏡学会の了承を得なければならない。高橋と風戸は二人で日本電子顕微鏡学会会長・瀬藤象二を訪ね、理解を得ることができた。
当初自ら参加するつもりのなかった高橋だが、伊藤と二人の参加を連絡したフランスから、歓迎の言葉と、一等航空運賃および滞在費一切が贈られる厚遇を受け、「夢のような話」と喜びながら発表の準備にとりかかった。一方、再三、風戸に金の苦労を報告していた伊藤に対しても、主催者はロンドン国際会議の実績を認め、フランス国立研究所研究員並の給料を3ヵ月支給する異例の処遇を提示した。さらに、シンポジウムオルガナイザーのフェルト教授は、伊藤に「電子顕微鏡の今日の問題」をテーマとして、シンポジウム冒頭に40分の基調講演を依頼してきた。伊藤は奮い立ち、この大任を見事に果たした。
シンポジウムは4日間にわたり、各国の重鎮に混じって日本の高橋と伊藤も入れ代り立ち代わり講演を行った。予想通りその後非常に激しい討論が延々と続けられた。激しすぎて、閉会後に何人かは疲れてダウンしたほどだった。
伊藤は報告している。「電子顕微鏡およびその応用のみならず、学問的レベルに於いても、日本は決して外国に劣らないことを世界に認めさせたことは愉快です。この会のあとでは、誰も日本の電子顕微鏡が単なる真似であるとは言わなくなったのは事実です」。
高橋も風戸に寄せた所見で、伊藤が基調講演と本講演で日本の電子顕微鏡の現状を説き、JEMに関する十分な説明をしたことは、CNRS主催の国際学術講演会が、期せずしてJEM電子顕微鏡の宣伝に異例の貢献をしたことを指摘している。
実際に日本電子の電子顕微鏡のレベルが高かったこと、電子回折分野で結晶学の研究レベルがすでに国際的評価を得ていたこと、そして、JEMの性能が優れていたことが、これほどの評価を受けた背景にあるが、それ以前に高橋の長年の努力がCNRSのデュピュイ、トリヤ両博士に日本の電顕、電子回折の実力を認めさせていたことがものを言った。
さらにベルギー・ゲント大学で「日本電子顕微鏡デー」が開催された。駐ベルギー大使代理、ゲント大学総長、ヨーロッパ電子顕微鏡学会々長、ベルギー電子顕微鏡センター所長などが勢揃いし、盛大に行われ、見本の実物さえないのに、日本電子の電子顕微鏡は絶賛された。これはとても信じられない不思議な出来事に思えてならない。
オランダ・フィリップス社からは大学教授ら3人、ドイツからもツァイスの研究所から研究員が来て、激しい論争を挑んできたが、伊藤一夫は堂々と渡り合い、ますます日本電子の製品の優秀性がアピールされた。つまり日本の最も小さな顕微鏡メーカーが、学術的にも評価される方法で他の企業が想像もつかない大宣伝を行ってしまった。
風戸の輸出への努力も進められ、日本側の輸出代行業務を三菱商事に依頼することは決まった。商事の担当者もヨーロッパでの日本電子の評判を知って大いに興味を燃やしてくれた。折りも折り、ベルギーから連絡が入った。「設立計画中の工業化研究所は日本電子の4型と5型の電子顕微鏡の予算を計上し、カタログどおりなら必ず購入する」。フランスからもいくつか有力な引き合いがあり、「万一成功しなかったときにも三菱商事に迷惑はかけない」。風戸はそんな一筆を書いて三菱商事に見本輸出を依頼した。担当者も熱心に動いてくれて、この計画は実現するかに見えた。しかし、「過去において日本製の高級電気機械が欧米先進国に輸出された例がない」、こんな理屈で上層部が受け付けなかった。
一方、高橋は、’54年ロンドンの国際学会で伊藤一夫に金を用立てた経験から、日本電子の台所事情を察し、逆転の発想をしようと決心する。
「トリヤを日本に連れて行き、その目で日本電子の電子顕微鏡を見てもらうしかない」
けれど多忙なトリヤ教授が大義名文もなく日本まで来てくれるわけがない。
彼を日本に往かせる名目は何か、金のない日本電子に代わって教授を招待してくれそうなところはどこか、高橋は必死に策を巡らせた。一石二鳥の方法は文化使節として招待することだった。ちょうど理研の主任研究員で、日本応用物理学会々長の辻二郎が何回かパリに来ていた。高橋は一心に辻を口説いて教授を文化使節として日本に招待する話を進めた。幸い辻は本気になって骨を折ってくれ、その顔の広さのおかげで、電子顕微鏡学会、結晶物理学会、そしてフランス外務省が協賛してくれることになった。
(つづく)