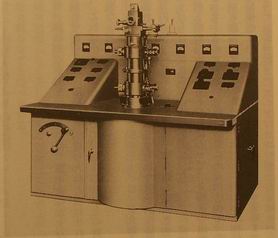風戸裕の短すぎた生涯[24]第7章 「裕、不運な低迷の中でも輝きを放つ」⑥
 photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より
photo:ビル大友・著「レクイエム風戸裕」より
決勝では初めての好ポジションで気を良くし、ヒート1のスタートで猛ダッシュ、第1コーナーまでになんとトップに出ていた。ストレートでヨッヘン・マスに抜かれ、次のストレートでアンリ・ペスカロロにも抜かれ、3位のまま戻ってきた最終コーナー、突っ込みすぎてブレーキがロック、コースアウトしてしまい15位まで落ちてしまった。ところが、その後はひたすら追い上げ、最終ラップではペスカロロ、アンドレア・デ・アダミッチまで抜いて6位でフィニッシュした。スタートのフライングを取られ、1分加算のペナルティで10位になったが、なんと、風戸裕は観客のハートをガッチリとつかみ、最大の拍手を浴びたのである。
【登場人物】
風戸 裕=フジで事故死したレーサー。
風戸健二=その父。日本電子創業社長。
ヒート2でも快調に飛ばし、4周目までにマス、スタック、C・バンダーベル、J・クーロンに続く5番手につけた。しかし、またまたヘアピンでスピンをやらかし、なんとか挽回、7位でフィニッシュした。ヒート1、2合わせて総合6位、グレーテッドドライバーがいたので、念願のポイント2を獲得した。
マネージャーの稲垣忠志は別行動で、このホッケンハイムのヨッヘン・リント・メモリアルトロフィーレースには遅れて到着したのだが、遅れたことをすごく悔やんだ。というのも、第1ヒートも後半で、風戸裕の白いGRDは明らかに下位を走っているのだが、サーキットは「ヒーロシ!」「カザート!」の声援一色。稲垣は裕が場内の人気を独占しているのに気づいてびっくりした。
「なんで?」「何があったの?」。そう思う間に白い裕のGRDは何台ものマシンをごぼう抜きし、そのたびにスタンドは湧き、最終ラップにペスカロロとアダミッチを抜いてゴールしたときは、観客は総立ち、サーキット全体が騒然となり、いつまでも拍手が鳴り止まなかったのだ。
ホッケンハイムの観客はおよそ20万人! 想像できるだろうか。地元のヨッヘン・マスの勝利に大拍手を送ったのだが、風戸のゴールインでは観客席を中心に地面が揺れるほどの大歓声が上がった。テレビのアナウンサーもすっかり興奮して「ヒーロシ、ヒーロシ」と連呼するばかりだった。フライングの判定にも観客はブーイングを送る。
風戸は走りで観客の心をとりこにしていた。それまで2年間、風戸のファイトを信じつつも、どこか物足りなさと不安を抱いてレース結果を見てきた稲垣は、この瞬間吹っ切れた。「やっぱり風戸だ」。急いで稲垣がピットに駆けつけると、裕はまだ興奮冷めやらぬ口調で言ったのだった。「ああー、レースやっててよかった」。
こんな言葉は初めて聞いた。
稲垣は素直に、遅れて途中からしか見ていないことを伝えた。すると、裕もその場にいた誰も彼もが、吾がことのように悔しげに顔をゆがめる。それでも、裕がスタートでトップに立ったこと、そのスタートは見たこともないような素晴らしいダッシュだったことを口々に話した。
稲垣はそこで初めて見逃したものの大きさに気づく。まさに痛恨の思い。「風戸はそれまで見たことのない、何かをつかんだような良い目をしていたし、全身から躍動する熱気を発散させ、別人のようだった。フライングのペナルティは時の運で、風戸にとっては最高のスタートが切れたし、それは風戸が苦労してつかんだものを発揮した瞬間だった。スピンも誰よりも激しく攻めた結果だった。下位から追い上げる風戸の姿にも風戸がつかんだ何かが光って見えたのだろう。本場のレースファンはそれを見にきているんだなと教えられた。風戸は彼らに完全に認知されていた」。
私も、後に稲垣からこの話を聞いて初めて合点した。
実は、レースダイアリーは成果の伴わないレースの繰り返しで、私はスピンやクラッシュを焦りのせいとばかり思っていたし、その他のミスも重なりGRDのままでは裕は本場ヨーロッパのレース関係者に認められることはないのではないかと、真剣に心配していた。目標がF1で、そのステップとしてのF2にしては出来が悪すぎると感じていたからだ。
常にひたむきな裕のレースへの姿勢をヨーロッパのファンが愛し楽しんでいた以上に、レース関係者も裕のファイトを高く評価し始めていたに違いないと思えるようになった。
裕のレースは成績を超えて彼らの魂を捉えていたのだ。そうは言っても、裕のF2挑戦は決して軌道に乗ったわけではない。
6月24日、ルーアン(フランス)ではシケインに触れてフロントを曲げてしまい、路面が濡れているのもかまわず前車をコーナーのアウトから抜きにかかってスピン、ガードレールに激突、それで終わった。「勝利の女神は一度として僕のところへきてくれない。ユーウツ。『自分が悪い』で済ませればいいのだろうが……」。裕は、マシンが調子よく、自分がミスさえしなければ、優勝できるとさえ感じていた。実際そうだったのだろう。だからこそ、現実との落差に苦しんだ。
’73年7月29日はスウェーデン・マントープパーク。やっとシュニッツァーチューンのBMWエンジンを手に入れ裕は期待に胸を膨らませる。だが、2ヒートともスタート直後の第1コーナーで終わってしまった。20台の車がかき回す力でゴミが詰まり、アクセルが動かなくなってしまったのだ。
あっけない結末に裕は力を落としたが、自分に言い聞かせている。「またダメだったが今度がある」。8月12日は同じスウェーデンのカールスコーガ。今度は最終ラップにドライブシャフトが壊れてリタイアした。
8月26日はイタリア・シシリー島のエンナサーキット。やっとシュニッツァーの手応えがあって昨年より4秒も早いタイムで予選順位は5位。何人かのF1ドライバーより上で非常に気分を良くしていた。ところが、腹の調子が悪くなってきた。症状はコレラと同じという、悪名高き「エンナ下痢」だった。決勝前夜は腹痛で一睡もできず、食事も水もとれないほど。サーキットに行くまでも全くひどい状態で、とりあえずスタートしたものの、途中、やはり続けられずレースを断念した。結果の出ないシュニッツァーがやっと本調子になったというのに、裕は泣くに泣けない気持ちだ。
生沢徹はF2から撤退し、日本のGCレース一本に絞った。
(つづく)